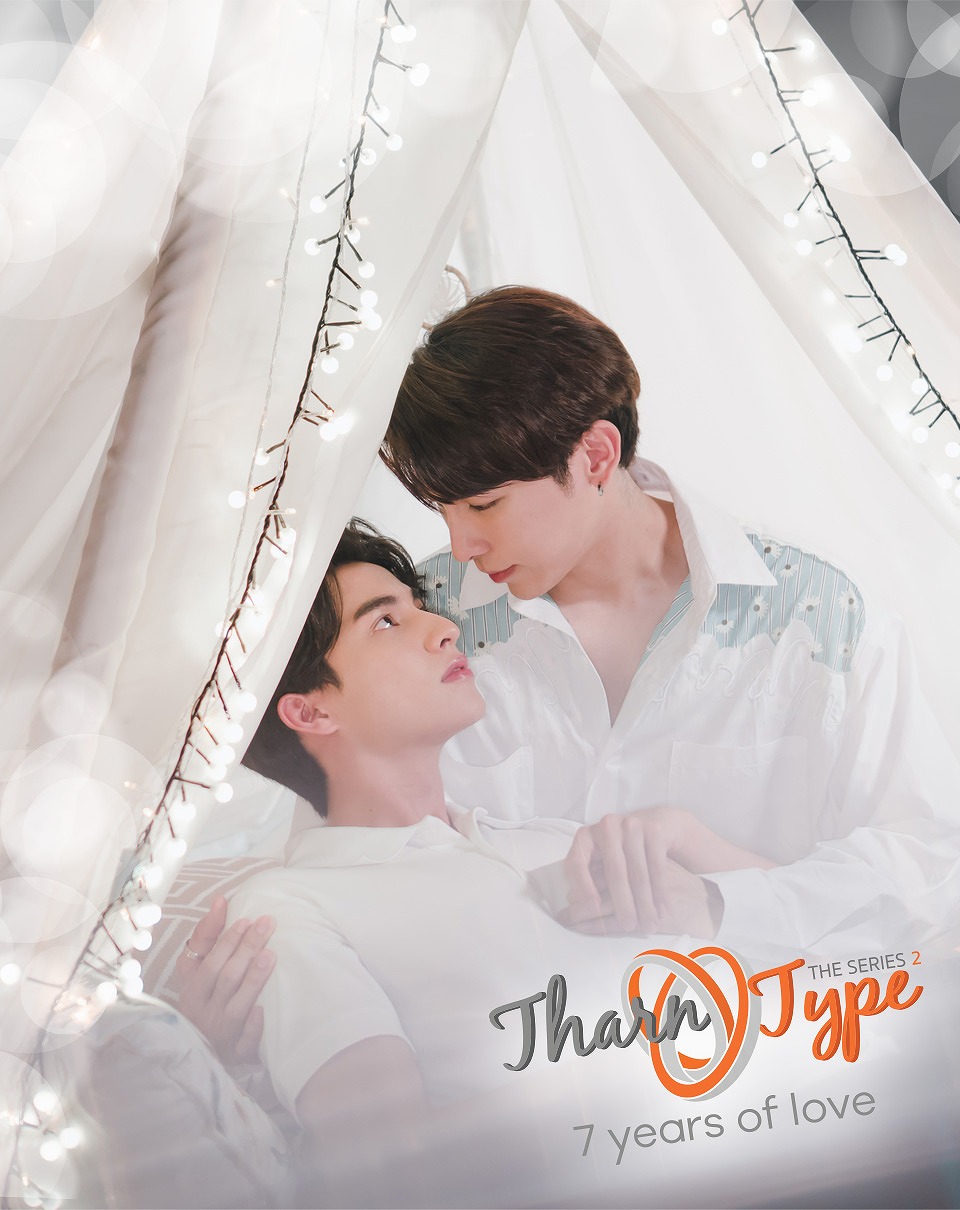- Home
- もっと知りタイランド
- タイ「微笑みの国」のフレーズは、こうして生まれた?! 文化か?戦略か?
タイ「微笑みの国」のフレーズは、こうして生まれた?! 文化か?戦略か?
- 2025/8/4
- もっと知りタイランド

タイは長年、「微笑みの国(Land of Smiles)」として知られてきました。
このフレーズは、タイ人の温かさ、ホスピタリティ、そして文化的魅力を象徴するものとして広く使われています。
しかし、このフレーズは、いつどこから生まれたものなのでしょうか?
タイの歴史家や文化評論家たちは、主に2つの起源説を提唱しています。
起源その①:戦後に芽生えた「シャイで優しい笑顔」
最初の起源は、第二次世界大戦後の時代にさかのぼります。
戦後、タイを訪れる欧米人旅行者が増えるにつれ、言語の壁がコミュニケーションの障害となりました。
英語を話せない多くのタイ人は、代わりに笑顔で対応したのです。
著名な作家であり元首相のククリット・プラモート氏によると、外国人たちはこの温かいジェスチャーに感動し、それを「シャムの微笑み(Siamese Smile)」と呼ぶようになったといいます。

起源その②:国家主導の観光戦略から生まれたキャッチコピー
もう一つの、より制度化された起源は1960年代にあります。
当時のサリット・タナラット首相のもとで、タイ政府は初の国家経済開発計画を立ち上げました。
その一環として観光産業の強化が図られ、「シャム、微笑みの国(Siam, the Land of Smiles)」というスローガンが採用されました。
このフレーズは国際的な旅行雑誌や広報キャンペーンを通じて積極的に発信され、外国人観光客を歓迎する温かく友好的な国としてのイメージが築かれたのです。

文化的な自然さから生まれたのか、それとも巧妙なブランディングによるものか…。
いずれにせよ、「笑顔」はやがてタイを象徴する国民的なシンボルとなりました。
今日でも、タイのホスピタリティを表す代表的なイメージとして世界中に知られています。
しかし本当のところはどうなのでしょうか。
「微笑みの国」という称号は、見事なマーケティング戦略だったのか、それともタイ人の本質を映し出す本物の文化なのか…?
その答えが気になって、今日も夜しか眠れません。